も
◆モービル
mobile
「モバイル」ともいう。アマチュア無線では車で移動運用することをいう。一般には、携帯電話などで通話・通信をおこなうことをモバイル通信(移動体通信)といい、移動先でノートパソコンなどをインターネットにつないで通信をおこなうことをモバイル・コンピューティングという。
◆モールス
Samuel F. B. Morse
モールス符号を考案したサミュエル・モールス(Samuel Finley Breese Morse)というアメリカ人(1791〜1872)。1810年、エール大学を卒業。1835年にニューヨーク市立大学の美術学教授となり、また画家としても活躍し始めた。1832年、欧州からアメリカへ向かう大西洋上の船で、乗客の一人からファラデーが電磁誘導の研究に成功した話を聞いて、電磁石を利用すれば有線で符号通信ができると考えた。こうして帰国したモールスは遠隔地のベルを鳴らす試みに成功する。モールスは、ニューヨーク市立大学の学生だった16歳年下のアルフレッド・ベイル(Alfred Vail、1807-1859)の協力を得て、現在のモールス電信符号の体系を作り上げた。1837年にはモールス符号を用いた印字電信機を開発した。1844年5月24日にはアメリカ東海岸のワシントンDCとボルチモアの間で通信実験がおこなわれたが、このときモールスが用いた電文は「What hath God wrought」(神の御業により創造し給うたもの)であった。モールスは後に電信会社を創業している。写真とイラストで故人を忍ぶ。
サミュエルキーとも呼ばれている1844年-1845年当時の電鍵

Photo by Kent
ありし日のモールス
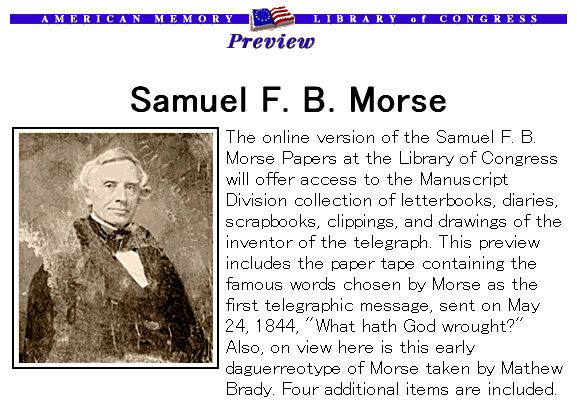
◆モールス符号
morse code
モールスコードともいう。サミュエル・モールスとアルフレッド・ベイルが考案した通信コード。英文のアルファベットのうち、出現頻度が高いEに「・」を、Iに「・・」を割り当てるなどしてモールス通信の効率化に貢献したのはベイルその人である。
当初は紙テープに印字したり穴を開けたりしていたが、現在では電鍵が伝える電気信号の有無を無線機が読みとって電波の搬送波の有無に直して送信し、受信側は低周波信号の有無の音響(トンツー)に変換して情報を読みとっている。何かの理由で電波が使えない場合、海上で投光器を使って光でモールス符号を送受することもある。アマチュア無線が始まったのはいつかについては諸説があるが、1902年、または1910年ないしはその数年後、モールス符号を使った形式でスタートしたと言われている。郵便局は1963年(昭和38年)にモールス符号の電信による電報を廃止した。
アルファベットや数字を入力すると自動的に音に翻訳するサイト
欧文のモールス符号が基台の表面に刻まれている珍しい電鍵

© OZ2CPU
◆文字通信
text communication
文字(テキスト)を送受する通信形態。アマチュア無線ではRTTY(ラジオテレタイプ)やパケット通信(アマチュア・パケット無線)が代表的。文字を画像として送受するファクシミリ通信は画像通信に分類されている。「RTTY」「アマチュア・パケット無線」を参照。
◆モデム
modem / modulator demodulator
変調と復調の機能を1つの筐体か基板に備えている通信装置(変復調装置)。インターネットにダイヤルアップで接続するモデム、DSLサービス用のDSLモデム、CATVインターネット用のケーブルモデムなどがある。
◆モニター
monitor
コンピュータのディスプレイのこと。リグの作動状態を監視すること。
トップページへ戻る