周知のように7MHz帯や3.5MHz帯など9MHz以下ではLSBが用いられているし、14MHz帯や21MHz帯など9MHz以上ではUSBが用いられている。なぜだろう。 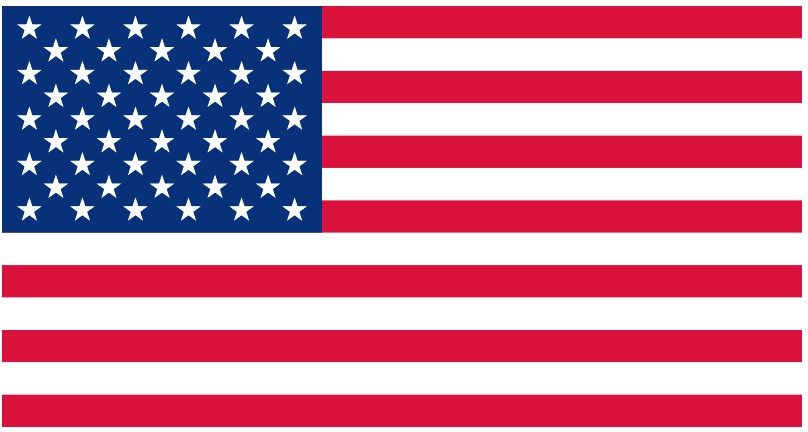 1950年代後半以降の初期のSSBトランシーバの電気回路構成を思い出してみよう。当時、一般的に使われていたSSBのためのキャリア発信器の一つに9MHz(当時は9Mc:9メガサイクル)の発信器があった。従って当然だが9MHz以下ではLSB、9MHz以上ではUSBになった。これは自動的にそうなっていたので、特にUSB/LSBの切替スイッチは無かった。ただしこの経緯に対して異論を唱える人もいるのは事実だ。別の説だが、9MHz(当時は9Mc)のキャリア発信器の他に、米海軍放出の格安な航空機用送信機 ARC-5 aircraft をミキサー用のVFOとして使った人も多かった。そのころ最もポピュラーなバンドは3.8MHz帯と14MHz帯だった。9MHzから5.2MHzを「下げ降ろせば」3.8MHzになるし、9MHzに5MHzを「上乗せ」すれば14MHzになる。サイドバンド(側波帯)も同様に「下げ」「上げ」になった。こうして3.8MHz帯ではLSBが、14MHz帯ではUSBがそれぞれ当たり前のように使われるということになった。この説に対して、必ずしも ARC-5 と「9MHzルール」とは関係ないという人もいる。
1950年代後半以降の初期のSSBトランシーバの電気回路構成を思い出してみよう。当時、一般的に使われていたSSBのためのキャリア発信器の一つに9MHz(当時は9Mc:9メガサイクル)の発信器があった。従って当然だが9MHz以下ではLSB、9MHz以上ではUSBになった。これは自動的にそうなっていたので、特にUSB/LSBの切替スイッチは無かった。ただしこの経緯に対して異論を唱える人もいるのは事実だ。別の説だが、9MHz(当時は9Mc)のキャリア発信器の他に、米海軍放出の格安な航空機用送信機 ARC-5 aircraft をミキサー用のVFOとして使った人も多かった。そのころ最もポピュラーなバンドは3.8MHz帯と14MHz帯だった。9MHzから5.2MHzを「下げ降ろせば」3.8MHzになるし、9MHzに5MHzを「上乗せ」すれば14MHzになる。サイドバンド(側波帯)も同様に「下げ」「上げ」になった。こうして3.8MHz帯ではLSBが、14MHz帯ではUSBがそれぞれ当たり前のように使われるということになった。この説に対して、必ずしも ARC-5 と「9MHzルール」とは関係ないという人もいる。
Rod Dinkins(AC6V)の見解 なお、SSBに関する「9MHzルール」はFCCのような公的機関が定めたものではなく紳士協定なので、7MHz帯や3.5MHz帯などの9MHz以下でUSBを使う人もいる。
有名な伝説的 DX-peditioner のひとりに1960年代(1962〜1967年)、世界的に活躍した米国イリノイ州シカゴ出身のドン・ミラー(Donald Alan Miller、W9WNV、その後はAE6IY)がいる。  鈴木肇OM(JA1AEA)によれば、ドン・ミラーは、1960年の初めごろに在韓米軍の烏山空軍基地に軍医大尉として駐留していた頃は HL9KH のコールサインでアクティブに出ていたという。DXペディションの後、アメリカ本土に戻った外科医のドン・ミラーは診療所を経営した。しかしテレビドラマ「逃亡者:The Fugitive」のリチャード・キンブル医師に似て「妻殺し」の疑い(ただし殺人未遂の容疑)をかけられ、結局は州刑務所に収監されてしまう。鈴木肇OMによれば、ドン・ミラーの妻は、当時、カルト教団に入信し、離婚して当時5歳だった息子を連れて教団の施設に入ると言い出したことから夫婦の争いが始まったといい、でっちあげで「妻殺し未遂」の冤罪(えんざい)により刑務所に収監されてしまったということである。 鈴木肇OM(JA1AEA)によれば、ドン・ミラーは、1960年の初めごろに在韓米軍の烏山空軍基地に軍医大尉として駐留していた頃は HL9KH のコールサインでアクティブに出ていたという。DXペディションの後、アメリカ本土に戻った外科医のドン・ミラーは診療所を経営した。しかしテレビドラマ「逃亡者:The Fugitive」のリチャード・キンブル医師に似て「妻殺し」の疑い(ただし殺人未遂の容疑)をかけられ、結局は州刑務所に収監されてしまう。鈴木肇OMによれば、ドン・ミラーの妻は、当時、カルト教団に入信し、離婚して当時5歳だった息子を連れて教団の施設に入ると言い出したことから夫婦の争いが始まったといい、でっちあげで「妻殺し未遂」の冤罪(えんざい)により刑務所に収監されてしまったということである。
鈴木肇OMらはドン・ミラーを刑務所から救出するために「極東DX基金」(FEDXF:Far East DX Foundation)と言う非営利団体を設立して弁護費用のための寄付金を募った。こうしてドン・ミラーは2002年6月に仮釈放された。 一方、長谷川亮一OMのウェブサイト「沖ノ鳥島とアマチュア無線」によると、ドン・ミラーは1963年に沖ノ鳥島で史上初のDXペディションをおこなったとされているという。当時、沖ノ鳥島を含む小笠原諸島は米国の占領下にあり、日本(JA)とは別のカントリー(エンティティ)とされていた。長谷川OMによるとドン・ミラーは「KG61D」のコールサインで1963年5月31日から6月2日までの約33時間にわたり沖ノ鳥島で単独運用を決行、2,379局と交信したとされるという。不思議なことに本来は「KG6ID」のコールサインになるはずが“タイプミス”のせいで「I」が数字の「1」(いち)になってしまったらしい(?!)。長谷川OMは「ほとんど陸地らしい陸地のない沖ノ鳥島で、いったいどのようにして3日間も無線局を運用したのかが気にかかるところだが、あいにくその点の詳細は明らかでない」という意見を述べられている。ちなみに長谷川OMはアマチュア無線家ではないが、海洋島嶼の環境については体験があるという。ドン・ミラーは1967年12月までDXペディションを繰り返したものの、その真偽について、さまざまな憶測が飛び交い、ARRLとの間で深刻なトラブルに見舞われるのである。
|
|||||